K:第二回は海モノでいこうと思うんだ。
A:へぇ。海モノというと……戦艦ですか?
K:微妙に違うね。今回説明するのは、「航空戦艦」!
じゃあ、艦艇の区別を大雑把にしてみようか。
ホント、大雑把な区別だからね。
○戦艦(Battleship)
分厚い装甲と巨大な主砲を持つ大型の艦艇。主砲で敵艦を叩きのめすのが主な役割。
第一次世界大戦までは海戦の主役だった。
しかし、性能の向上とともに建造にかかるコストも跳ね上がり、迂闊な投入はできなくなった。
実質、第二次世界大戦では、戦艦らしい活躍をできた船は非常に少ない。
航空機の性能のインフレ化とともに廃れ、フランスの「リシュリュー」級戦艦の二番艦「ジャン・バール」を最後に新規建造はなくなった。
1995年にアメリカの「アイオワ」級戦艦の4隻が揃って除籍され、ついに絶滅してしまう。
なお、装甲を犠牲にして速力を高めた「巡洋戦艦」というものも存在する。
○巡洋艦(Cruiser)
戦艦よりも小型。駆逐艦よりは大型で、高速。
偵察・魚雷戦闘(以降水雷戦)・砲戦と様々な任務をこなせる。また、小規模艦隊の旗艦として運用されることも多い。
第二次世界大戦までは排水量や主砲口径で「軽巡洋艦」と「重巡洋艦」に分かれていたが、今ではその区別はない。
現在ではSAM(対空)・SSM(対艦)・SUM(対潜)ミサイルを装備したミサイル巡洋艦や、10機ほどのヘリを運用できるヘリコプター搭載
巡洋艦などが運用されている。
また、非常に優れた索敵能力と火器管制能力を持った「イージス巡洋艦」というものもある。(アメリカのタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦)
なお、現在では定義が非常に曖昧で、保有している国が「巡洋艦」と主張すればその船は巡洋艦となる。
○駆逐艦(Destroyer)
巡洋艦よりもさらに小型。水雷戦・対空戦・対潜戦と様々な任務に投入された汎用性の高い艦種。
主に空母や戦艦といった大型艦の護衛や、輸送船団の護衛(日本海軍はこれを軽視していたが)などの任務を行う。
第二次世界大戦後は航空機やミサイルの性能のインフレ化に伴い、強力な対空・対潜能力が求められた。
また、大戦期は2000トンほどだった排水量は増大し、アメリカのイージス駆逐艦「アーレイ・バーグ」の満載排水量は8000トンを越え、
重巡洋艦「古鷹」型並となった。
なお、日本のイージス護衛艦「こんごう」型は、他国からは駆逐艦と見られている。
定義としては、5000トン前後で十分な対空・対潜能力を持つ船のことをさすが、こちらも曖昧である。
A:はーい、質問ですー!
K:ん? 何かな?
A:「イージス艦」って艦種はないんですかーッ!?
K:ないよ。勘違いしてる人が多いけど、「イージス艦」ってのは「イージス・システム」を搭載した軍艦のこと。
アメリカに2タイプ、日本に2タイプ、スペイン、ノルウェー、韓国に1タイプずつ。韓国は建造中だね。
イージス艦についてもいつか軽くやりたいね。
A:で、今回の「航空戦艦」っていうのは?
K:後にも先にも「伊勢」型の2隻だけ。
その理由についてはおいおい解説していくね。
それじゃ、本題に入ろうか。
A:はーいッ!
K:まず、この「伊勢」型が誕生した経緯について話しておこうか。
1906年、「ドレッドノート」っていう画期的な戦艦がイギリスで誕生したんだ。
○ドレッドノート(HMS Dreadnought)
同一口径の巨砲を搭載した初の戦艦。主砲のサイズが同一のため、射撃指揮が極めて行いやすく、遠距離砲戦で真価を発揮する。
しかし、この艦が就役してからの戦艦の発展スピードは凄まじく、あっという間に旧式艦になってしまった。
この艦にとって最も大きな戦果が「体当たりで潜水艦を撃沈」ということはあまりにも出来すぎた皮肉である。
K:この戦艦が「超ド級」の由来になってるね。
A:……あの、「同一口径の巨砲を搭載した」ってとこがよくわかんないんですけど。
K:ドレッドノート以前の戦艦には、目的によって別々の大砲を使っていたんだ。
敵艦の海面から出てる部分(水線部)に穴を空けるための主砲を艦首・艦尾に搭載、
敵艦の上部構造物(艦橋など)を破壊する副砲舷側に搭載。
それをそれぞれの砲手が指揮して、バラバラに撃ってたんだ。
それは距離が数千メートルまでは有効なんだけど、それ以上は通用しないんだ。
A:より高い命中率を得るために、大砲のサイズを一緒にしたんですね?
K:うん。日露戦争での「日本海海戦」では、射撃指揮を全部艦橋で行って、砲側じゃ一切修正しないって手法を採ったんだ。
それで、日本海海戦を徹底的に分析したイギリス海軍が導き出した回答が「ドレッドノート」なんだ。
A:そういえばさっきの解説で、「遠距離砲戦で真価を発揮する」って書いていましたね。
従来の戦艦と比較すると、どれぐらい強かったんですか?
K:「ドレッドノート一隻で、従来の戦艦2隻分の戦力を発揮する」って評価を受けたけど、遠距離砲戦じゃそれ以上だね。
ドレッドノートが就役したせいで、今まで就役してた戦艦は全部旧式の烙印を押されちゃってね。
イギリスの「ロード・ネルソン」級、フランスの「ダントン」級、日本の「薩摩」型なんかは、就役前に旧式化しちゃった。
以後、大艦巨砲主義が世界に蔓延し、凄まじい建艦競争が始まったんだ。
A:大艦巨砲主義というと、「でかくて大きな大砲を持つ戦艦が強い」って理屈ですね!
なんかダメダメな響きです!
K:まぁ、当時は戦艦が洋上の最強戦力だったんだからね。
ドレッドノートが就役して6年後の1912年には、彼女を装甲以外のあらゆる面で上回る「オライオン」級巡洋戦艦が就役し、超ド級戦艦の
時代を迎えたんだ。
A:6年後……滅茶苦茶スピードが速いですね……。
K:ま、航空機の進化スピードには劣るけどね。
そして、日本海軍は一つの超ド級巡洋戦艦をイギリスに発注したんだ。これが、太平洋戦争で大活躍することになる「金剛」型だよ。
○「金剛」型巡洋戦艦
36センチ連装主砲4基8門という高い攻撃力と、27ノットという脅威の速度性能を持つ優秀艦。
一番艦の「金剛」はイギリスで建造され、以降の「比叡」「榛名」「霧島」は図面を取り寄せて国内で建造している。
その高い能力は、第一次世界大戦でイギリスが「貸してくれ」と言ってきたほどである。
後の近代化改装でさらに速度が増し、30ノットまで増大。低速戦艦がメインで巡洋戦艦を保有していないアメリカを恐れさせた。
なお、「金剛」は、外国で建造された最後の主力艦である。
K:この「金剛」は優秀だったけど、所詮は防御力の低い巡洋戦艦。それに、設計はイギリス製なんだ。
日本海軍は、面子にかけて国産の超ド級戦艦を建造する。これが、「扶桑」型戦艦だよ。
○「扶桑」型戦艦
36センチ連装主砲6基12門という極めて強力な打撃力を持った戦艦。排水量も就役当時では最大で、各国を恐れさせた。
しかし、戦艦が世代交代する間に建造されたため、就役と同時に旧式化してしまう。
攻撃力は優秀だが、速力は滅茶苦茶に遅く、防御力にも問題のある艦。
そのため、太平洋戦争では全く活躍できないまま戦争終盤のスリガオ海峡で敵艦隊から集中砲火を浴び、姉妹揃って爆沈した。
一番艦は「扶桑」、二番艦は「山城」。なお、「扶桑」とは日本の美称の一つであり、この艦に対する期待のほどがうかがえる。
なお、一番艦「扶桑」の外見は極めて独特であり、二番艦「山城」とは大きく異なる。
K:この「扶桑」はとにかく問題の多い艦でね。当時は4隻作られるはずだったんだけど、2隻で終了しちゃったんだ。
それは設計の欠陥もあるんだけど、予算不足ってトコもあった。
で、3番艦以降は設計を改めて建造させることになる。これが、「伊勢」型だよ。
A:やっと出てきましたね! 前置き長すぎでした!
……でも、予算不足なんじゃ?
K:そう。だから、完全な新規設計は諦めて、「扶桑」型の悪い部分を直しただけにとどまったんだ。
○「伊勢」型戦艦
「扶桑」型の設計を改めて建造された艦。
問題のあった主砲配置を改め、副砲も口径は縮小されたが門数は増えた。(口径が縮小されたのは小柄な者が多い日本人の体格に合わせて)
防御力や速力も強化されているが、同世代の他国の戦艦に追いついたとは言い難い。
なお、居住性は最悪で、乗組員泣かせの艦だった。
一番艦は「伊勢」、二番艦は「日向」。
A:へ? 初めから「航空戦艦」なんじゃなかったんですか?
K:うん。最初は純粋な戦艦だった。
この「伊勢」型は、あくまでも「扶桑」型+α程度の性能しかなくて、海軍を満足させるものじゃなかった。
そんな海軍が建造した次の戦艦が、傑作艦として名高い「長門」型だよ。
○「長門」型戦艦
世界で初めて41センチ主砲を搭載した戦艦。
極めて高い防御力を誇り、速力も十分。建造当時では間違いなく世界最強の戦艦であり、各国の海軍関係者を大いに恐れさせた。
ルーズベルトが「日本はいつ占領できるのか?」と海軍関係者に問いかけたところ、「無理です。日本には長門がいます」と答えられたという
エピソードが残っている。
日本海軍のシンボルとして老若男女を問わず国民に親しまれた。
しかし、海軍の出し惜しみ体質のため太平洋戦争では全く活躍できないまま終戦を迎え、一番艦の「長門」は原爆実験に供されている。
一番艦は「長門」、二番艦は「陸奥」。
K:この頃の日本海軍は、「八八艦隊」計画というプランを立てていてね。この頃の仮想敵国はアメリカ。
その内容は、新型の戦艦8隻と巡洋戦艦8隻でなる最強艦隊でこちらに押し寄せてくる敵艦隊をボコボコにするっていった計画なんだ。
その艦隊決戦に向けて立案された作戦が、「漸減(ぜんげん)作戦」。この作戦を理解しないことには、太平洋戦争の日本海軍は理解できない。
A:そ、それぐらい重要な作戦なんですか?
K:うん。日本海軍の基本方針にして、極めてイレギュラーな手段に縋った作戦なんだ。
でも今回の主題とはあまり関係が無いから、省略するね。次回日本海軍モノに触れるときは、紹介するかもしれない。
A:重要な作戦なのに飛ばしちゃって大丈夫なんですか?
K:今回は主役はあくまでも「伊勢」だからね。
日本空母とか「大和」型戦艦に触れるときは必須だけど、伊勢じゃあまり関係ないから。
A:むー、引っ張られると余計に気になります。
K:気にしちゃ負けだよ。んじゃ、本題に戻るね。
ドレッドノートの登場で、世界中の国は躍起になって戦艦を建造する。所謂建艦競争だね。
でも、戦艦の建造費は莫大。このままじゃ、各国が建艦に金を使い果たし、共倒れになってしまう……!
それを危惧した偉い人たちは、「なぁ、ちょっと軍縮しようぜ」と会議を開いた。
これが、有名な「ワシントン海軍軍縮条約」だよ。
○ワシントン海軍軍縮条約
1921年にアメリカのワシントンDCで採択された条約。
アメリカ・イギリス・日本・フランス・イタリアの5カ国の戦艦の新規建造を禁止し、
戦艦・空母の保有量を5・3・1.75と定め、主砲サイズなども決められた。
しかし、保有量が決められなかった巡洋艦や駆逐艦などの開発が激化。
そのため、後に巡洋艦などの保有量を定めた「ロンドン海軍軍縮会議」が開かれることになる。
K:この条約のおかげで、日本海軍が計画してた「八八艦隊」計画もお流れに。
まぁ、実現したとしても国家経済が破綻するだけだろうけど。
A:日本の保有量が下げられたってあたりにアメリカやイギリスの思惑が見え見えですね。
わかりやすすぎます。
K:でもね、この「5:3」ってトコには凄いメリットがあるんだ。
そのメリットっていうのは何だと思う?
A:んー…………
K:逆に考えてみるんだ。
5:3ってことは、アメリカの戦艦保有量を日本の1.7倍に抑えられるってコトにならないかい?
A:アッー!!!
K:アメリカが本気になって戦艦作り出したら、日本は逆立ちしても勝てないからね。
コレぐらいの差なら、まだ個々の質でなんとかできるレベル。これで日本海軍は「月月火水木金金」の心構えで猛訓練に励むことになる。
A:量で勝てないなら質でって、まぁ当然の話ですね。
K:この頃の日本海軍が保有していた戦艦は、こんなトコだね。
全部で10隻。でも、「比叡」は条約によって練習戦艦になっているから、実際は戦力外だね。
「金剛」型……「金剛」「比叡(練習戦艦)」「榛名」「霧島」
「扶桑」型……「扶桑」「山城」
「伊勢」型……「伊勢」「日向」
「長門」型……「長門」「陸奥」
A:練習戦艦?
K:武装や装甲を一部取っ払って、訓練用にした戦艦のことだよ。
ワシントン軍縮条約には「廃棄しなければならない戦艦でも、非戦闘艦に改造すれば、その艦の保有は認められる」
って抜け道のような一文があってね。
それで、「比叡」が練習戦艦に充てられたんだ。この頃、彼女は天皇陛下の御召艦を何度か務めているね。
御召艦っていうのは、天皇陛下が大演習や観艦式で乗艦する艦のことだよ。
天皇陛下が乗っているわけだから、水兵達も普段よりも気合の入った動きを見せ、船の中もピッカピカに掃除されてたりするんだ。
K:で、ワシントン軍縮条約で戦艦の新規建造を禁じられちゃった。
さて、キミならどうする?
A:ん〜……「今ある戦艦をパワーアップさせる」か「戦艦に替わる兵器を開発する」?
K:両方とも正解だね。
でも、「戦艦に替わる平気を開発する」っていうのはここじゃ省略するよ。
この戦艦の新規建造を止められた時期…俗に言う「海軍休日(NAVAL HOLIDAY)」に、日本海軍は今までの戦艦に改装を施すんだ。
「伊勢」型も他の戦艦と同じく改装が施される。
まずは、1920年代に小規模改装が行われた。
○小規模改装
主砲仰角を25度→30度に引き上げ(より上を向けるようにして射程距離を伸ばす)
艦橋設備の強化
対空兵装の強化
偵察機(水上機)の搭載
主砲に測定儀(敵艦との距離や角度を測定する)を追加
K:で、「伊勢」型は、「長門」型に次ぐ戦力にならなければならないため、1930年代に大改装が行われたんだ。
この時期は、他の戦艦も相次いで大改装を受けているね。「比叡」も復帰してる。
○大改装
主砲仰角を43度まで引き上げ
防御力の強化
測定儀の強化
対空兵装の強化
機関を交換して馬力を強化・ボイラーの数が減ったため2本あった煙突を1本へ
機関交換に加え、艦尾を延長して速力を上げる
K:これは、「言うことを聞かない娘」(就役時)を「人並みに言うことを聞く娘」(小規模改装)に躾けて、
さらに「人並みの娘に英才教育を強いる」(大改装)みたいな感じだよ。
じゃ、大改装後の「伊勢」の雄姿を見てみようか。
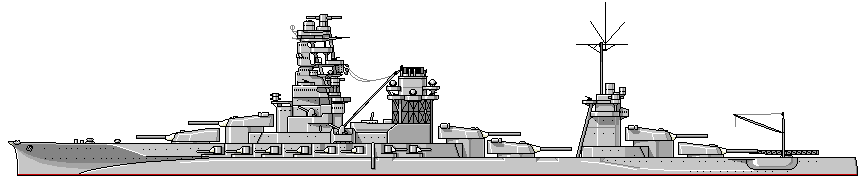
A:ずらりと並んだ主砲や副砲が頼もしいですね!
K:この「伊勢」型の位置付けは、戦艦戦力の中堅どころってところだね。
「扶桑」型よりは優れているけど、イマイチパッとしない……。
足が速くて便利な「金剛」型、艦隊決戦に温存の「大和」(開戦時には就役しておらず)「長門」型、
持て余し気味の「扶桑」「伊勢」型と、見事に3分されてたね。
A:……なーんか、活躍できなさそうな臭いがプンプンです……。
K:さて、1941年に太平洋戦争が開戦。
空母や巡洋艦・駆逐艦、それに海軍航空隊が制海権をめぐってし烈な戦いを繰り広げる中、「伊勢」型姉妹は訓練に甘んじる。
そして、日本海軍の一大博打であるミッドウェー作戦に参加するために猛訓練を行っている最中に「日向」の主砲が爆発。
多数の死傷者を出す大惨事が起こったんだ。
A:戦艦が主砲を失うって、大変じゃないですか……?
ほら、足をケガした陸上選手みたいな……。
K:うん。「日向」は応急処置として爆発した第5砲塔の部分に鉄板を張り、その上に3連装機銃を4基設置してミッドウェーに臨んだんだ。
結局、ミッドウェー海戦は4隻もの正規空母と多数の熟練搭乗員(他国であれば全員が教官レベル)に優秀な航空参謀を失うという
ボロ負けを喫してしまう。
ケガした「日向」も、「伊勢」も活躍できないまま帰還したんだ。
A:この敗戦から、日本は立ち直れなかったんですよね。
K:この時点で、日本は「やっべ、量産型の空母作ってなかった」と気付く。
そこで量産型の空母「雲龍」型の大量建造や、既存の戦艦を空母に改造することを決定したんだ。
A:こんな時に量産型の空母が無いことに気付くって、凄く間抜けじゃ…………
K:戦艦の改造は、「大和」型を除く全ての戦艦が改造対象になった。
でも、「金剛」型は旧式とはいっても30ノットの出せる高速戦艦だから、空母にするなんか現場が許さない。
「長門」型は未だに最強クラスの戦艦だから改造するのはもったいないし、「扶桑」型はトロすぎるからボツに。
そんなこんなで白羽の矢が立ったのが「伊勢」型。しかも同型艦の「日向」は損傷中。
と、いう訳で「伊勢」型は空母に改造されることになったんだ。
A:戦艦を空母に改造するって、大変な作業なんじゃないんですか?
K:うん。完全な空母にするのは時間がかかりすぎるということでボツに。
だから、後部に飛行甲板を据え付けて「航空戦艦」という形にすることにしたんだ。
発艦はカタパルトを使って発艦できるから問題はないんだけど、飛行甲板が短すぎるせいで着艦は不可能に。
A:え? じゃ、出撃させた飛行機はどうやって回収するんですか!?
K:同時に作戦行動を行っている空母に着艦させるか、近くの基地に着陸させる。
A:で、でも、空母にも飛行機があるんじゃ……
他の船から発進した飛行機を回収する余裕なんかあるんですか?
K:これは「飛行機が減る」ってコトを前提とした凄くネガティブな計画なんだ。
でも、搭載機として予定されていた艦上爆撃機「彗星」の開発が間に合わなかったから、代わりに水上機「瑞雲」を搭載することになったんだ。
「瑞雲」は水の上に着水できるから、後は設置されていたクレーンで回収すればいいからね。
で、2隻で44機の飛行機が運用できるから、中型空母並の戦力を発揮できる訳だ。
A:……なんとか形にはなったけど、誤魔化し誤魔化しでダメそうな雰囲気ですね……。
K:航空戦艦にするために施された改装は、こんなところだね。
それじゃ、航空戦艦「日向」の雄姿を見てもらおうか。
○航空戦艦への改装
第5・6番主砲を撤去して飛行甲板・格納庫を設置
対空兵装の大幅な強化
副砲の撤去
新型カタパルトの設置
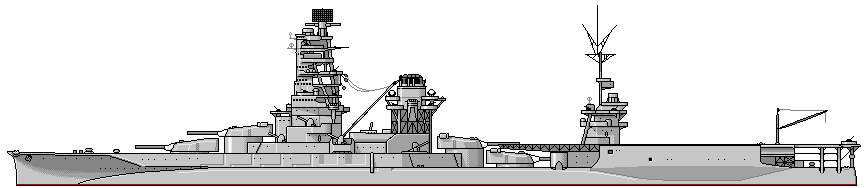
A:んー、主砲の後ろに飛行機を発進できそうなスペースがありますね。
なんとなく「こんなもんか」と納得しちゃいます。
K:さて、結論から先に言わせてもらうと、「伊勢」型が航空戦艦としての真価を発揮したことは一度もない。
A:えええええ!?
K:だって、積むべき飛行機が無かったんだから仕方ないよ。
もっとも、飛行機積んでたところで活躍できたとは思えないけど……。
A:ダメじゃないですかー!!!
K:結局、航空戦艦に改造された「伊勢」と「日向」が実戦に参加したのはフィリピン上陸阻止作戦「捷一号作戦」のみ。
これは空母部隊を囮にして敵の空母部隊を釣り上げて、フィリピンに上陸しようとする輸送船団を戦艦をメインとする部隊で
ボコボコにするっていった日本海軍最後の大博打。そして、人類史上最大の大海戦。
その大海戦に「伊勢」型姉妹は囮部隊として参加したんだ。飛行機を1機も積んでないほとんど戦艦と同じ状態で。
A:へ? そんなハリボテ同然の航空戦艦を参加させてよかったんですか?
K:だって囮部隊だからね。ちょっとでも本気っぽく見せたほうがいいでしょ?
囮の空母部隊は期待通りアメリカの恐るべき大機動部隊―20世紀の無敵艦隊―を釣り上げる。
アメリカからしてみれば、空母を囮にするなんて考えられないことだったからね。
A:なんで空母を囮に……あ、飛行機がないからですか?
K:うん。シミュレーションゲームやったことのある人ならわかると思うけど、飛行機のない空母なんか単なる鉄の箱でしかないからね。
日本の空母部隊は空母4隻に航空戦艦2隻、軽巡洋艦3隻に駆逐艦8隻。旗艦は真珠湾以来の歴戦空母「瑞鶴」。
この「瑞鶴」は姉の「翔鶴」と幸運と不幸を分け合った船でね。「翔鶴」はボコボコにされたけど「瑞鶴」は無事ってパターンばっかりなんだ。
A:なんか「翔鶴」が体を張って妹である「翔鶴」を守ってたように思えますね。
なんだか切ないです……。
K:そして、アメリカの大機動部隊を見事釣り上げた日本の機動部隊は、エンガノ岬沖でついに激突する。
400機を超えるアメリカ艦載機の猛攻の前に、空母「瑞鶴」「千歳」「千代田」「瑞鳳」は沈没。「瑞鶴」の沈没前の写真は残っているね。
A:……こんな状況でも、万歳するんですか……
K:……彼らの名誉のために言っておくけど、彼らは決して気が狂っているわけでもないし、狂信者の集団なんかでもない。
軍旗を降ろし、沈みゆく「瑞鶴」に対して精一杯の賛辞を送っているんだよ。もう一枚、「瑞鶴」に対して敬礼する写真もある。
海の男たちにとって、今まで共に戦ってきた艦への愛着は独特のものがあるんだろうね。悲しい写真であることに間違いはないんだけど。
A:……それで、「伊勢」と「日向」の活躍は?
K:うん。この航空機の猛攻の前には戦艦なんか無力かと思われたけど、「伊勢」姉妹はただの戦艦じゃない。航空戦艦なんだ。
爆弾を片っ端から避けまくり、新兵器の対空噴進砲(対空ロケット)や格段に強化された対空兵装で逆に70機近い敵機を叩き落してる。
A:す、凄い活躍っぷりですね!!!
K:しかも戦闘中に足を止めて、沈んだ空母「瑞鶴」の生存者を救出するなんて離れ業までやってのけている。
A:戦闘中に足を止めるなんて……自殺行為じゃないですか……。凄い……。
ダメだと思ってたのに、裏切られた気分です。
K:結局この作戦は戦艦部隊を率いる栗田中将の「謎の反転」でパーになっちゃう。
この「謎の反転」について詳しく述べるとまた長くなっちゃうから省略。
ま、簡単に言うと目標を前にしながらクルリと背を向けちゃって反転しちゃったってトコかな。
A:ほえ? どーしてですか?
K:それは栗田中将が墓の中に持って行っちゃったから永遠に謎のままだね。
で、この作戦で海軍は事実上壊滅。作戦行動も取れないぐらい燃料も枯渇しちゃったんだ。
そこで、「伊勢」姉妹に「格納庫に石油やゴムを積めるだけ積んで現在地のシンガポールから日本まで帰って来い」っていう任務が下された。
シンガポールから日本への制空権・制海権は完全にアメリカに握られ、潜水艦や航空機がウヨウヨ。
海軍内でも成功率は20%以下と見られていた極めて危険な任務なんだ。
この任務は「北号作戦」と称され、部隊は作戦完遂を祈って「完部隊」と名づけられた。
○完部隊(指揮官:松田千秋少将)
戦艦「伊勢」(旗艦) 「日向」 軽巡洋艦「大淀」(水上偵察機用の格納庫あり) 駆逐艦「朝霜」「初霜」「霞」
K:こうして2月10日、補給物資を満載した完部隊はシンガポールを出発する。順調に行けば、日本までは10日間の予定。
そして翌日、完部隊はアメリカの潜水艦に発見されてしまう。
A:早ッ!!!
K:完部隊の後を索敵機がついてくる。そして、完部隊も覚悟を決めた2月13日、ついにアメリカ軍の攻撃が始まった。
A:た、大変ですっ!! 石油とか満載してるから、ちょっとでも食らえば火だるまですよっ!? 逃げて逃げてー!!!
って、最初っから逃げる気マンマンですね。
K:完部隊に80機以上の敵機が襲い掛かったんだけど、ちょうどいいところにスコールが発生。完部隊はすかさずスコールの中に逃げ込んで
難を逃れたんだ。
A:な、ナイススコールですねっ!!!
K:そして1時間ほど経った後にアメリカ潜水艦が襲い掛かる。潜水艦は8発の魚雷をぶっ放したんだけど、神業的な操艦で全て回避。
翌日もアメリカ機に襲われるんだけど、そのときもスコールが発生したからその中に逃げ込んで難を逃れたんだ。
A:す、凄いっ!!! 高い技術と幸運の相乗効果ですねっ!!!
K:そして予定通りの2月20日、完部隊は一隻の脱落もなく呉に到着。
久々の大成功に、涙を流した将官もいたんだって。
A:……凄いなぁ。これって、「伊勢」姉妹にとって最高の戦果なんじゃないんですか?
K:うん。後の人は「伊勢」型航空戦艦をこう呼んだよ。
『史上最強の輸送艦』って。
A:あ、あはは……シャレになってないですね……。
K:この後、姉妹揃って呉に停泊。動くにも燃料がない状態だったからね。
そして1945年の7月に、呉を襲った大空襲で、姉妹揃って大破着庭(船底が海底まで沈むこと)してしまうんだ。
戦後は引き揚げられてスクラップに。
A:……なんだか、ほんと鏡写しみたいにそっくり同じ艦生を送ってますね。
K:そうだね。これだけ姉妹揃って同じ運命を辿った船も珍しい。
最後に、航空戦艦についてまとめてみるよ。
結論だけ言えば、戦艦と空母、お互いの長所を殺してしまっただけだね。
A:へ? 長所を集めた訳じゃないんですか?
K:戦艦の命は主砲。主砲発射時の爆風はデリケートな飛行機の部品に悪影響を与えるし、砲撃中の着艦は不可能。
戦艦として扱うにも主砲の数を減らしちゃってるし、空母としても短すぎる飛行甲板のせいで扱えない。
いわば、「帯に短したすきに長し」だね。
A:むー……万能兵器…………
K:言うならば、万能な兵器なんかこの世に存在しないんだよ。
「航空戦艦」は、切羽詰った国が苦し紛れに出した、砂上の楼閣だったんだ。
A:……じゃあ、コレはなんなんですかー!!!!

K:う……
A:提督の決断でも毎回「出雲」型航空戦艦を設計してるじゃないですかー!!
K:……仕方ないだろっ!! 航空戦艦は男の浪漫なんだよぉーっ!!!
A:そんなわけで、今回はここまでです。
リクエストなんかあったらどしどしお寄せくださいねっ!
それでは、しーゆーあげいん♪
K:航空戦艦ーーーっ!!!